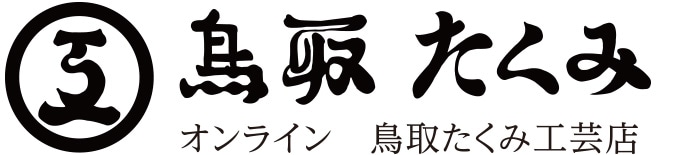2020/08/16 00:36

延興寺は海辺の浦富から10kmほど遡った谷にある、自然豊かな農村です。延興寺窯の山下清志さんは兄の影響で陶芸の道を志します。生田和孝(※1)の元で修行し、明治期に廃絶した岩美町の浦富焼を兄弟で再興。その後同じ岩美町で陶土が採れる土地を見つけ、1978年に登り窯を築き独立しました。岩美で採れる土にこだわったのは、昔ながらの民窯のあり方に近づきたいと考えたから。地元の土と、岩石や籾殻から作る釉薬、そこに人の手が加わって、土地から生まれる器となります。

「李朝のような焼物を作りなさい。」延興寺窯の山下さんが今でも振り返る師匠の言葉です。真意を聞くことはついにありませんでしたが、柳宗悦(※2)が民藝の思想に至るきっかけとなったのが、李氏朝鮮時代の白磁壺だったことから「民藝の原点を見よ」との意味だと解釈しているそうです。先人が作った物をよく見て学ぶことを大切にしている山下さん。鳥取には鳥取民藝美術館があり、創設者の吉田璋也(※3)がその審美眼をもって蒐集した古民藝の数々が保管、展示され、作り手は手に取り見ることを許されています。山下さんは若い頃から出入りし、今尚蒐集品から新たなアイデアを得ています。そして一家団欒の場でこういう器でご飯を食べたい、お茶を飲みたい、料理を盛りたい、と食卓を思い描きながら暮らしが豊かになる器を作り続けています。

谷を渡る風が心地よい新しい工房。低く響く音は娘の裕代さんの電動ロクロです。高校を卒業後沖縄県に渡り、北窯の松田共司さんの元で修行しました。跡を継ぐよう言われた事はなかったそうですが、父の仕事を見て同じ道に進んだそうです。延興寺に戻って十数年、仕事は続けるほど楽しくなってきたと言います。「沖縄で学んだことを土台に、父から吸収し、引き継いでいきたい。」静かな口調で語ります。工房にはもう一人、作業台で型に粘土を盛る、弟子入りしたばかりの男性。都会の出身で、30代後半まで陶芸とは無縁の仕事をしてきたと話します。自然豊かな地で暮らしたいという希望を叶え、岩美町へ移住して数ヶ月、一人前の作り手になるため精進の日々だそうです。

静かに蹴ロクロを回す清志さん。吉田璋也が育んだ鳥取民藝は、師匠から弟子へ、弟子からその弟子へ脈々とを未来へ継承されていきます。
※1生田和孝:1927-1982鳥取県東伯郡中北條村(現北栄町)生まれ。河井寛次郎に師事し、丹波立杭(今田町釜屋)に窯を構えた陶芸家。
※2柳宗悦:1889-1961 民藝運動を起こした思想家。
※3吉田璋也:1898-1972 鳥取の医師であり、新作民藝のプロデューサー。鳥取民藝美術館、たくみ工芸店、たくみ割烹店を開く。