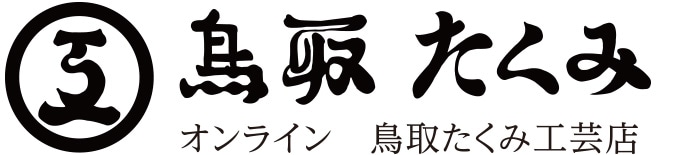2020/08/15 17:30

鳥取県倉吉市不入岡(ふにおか)は古くは伯耆国の中心であり、明治期には日用の民具や土管が焼かれる窯場でした。国造焼4代目となる山本佳靖さんは30代の若い窯主です。歴代の当主が個性的な陶器を作ってきた国造焼が、民藝の窯として歩み出したのは当代になってからのこと。もともと先代が極めてきた焼締(※1)の技法で一点物の工芸品を作る作家である山本さんは、県内の若手デザイナーと取組んだ物作りの企画展をきっかけに、民藝との繋がりを深めます。恒例の鳥取民藝美術館の展示設営にも携わり、収蔵された古作や新作民藝の品々から新たな学びを得るようになりました。
一点の製作に数日かける作家の製作とは対照的に、決まった形の製品を黙々と量産する器作りは職人仕事だと言います。無心に手を動かす作業の中で焼締のアイデアが浮かぶなど、一見全く別ものに見える作風を行き来することが、器の質の豊かさを生むのかもしれません。
国造焼の器で代表的な、細い線が連なった模様は飛鉋(とびかんな)で土を削ったもの。鉋のしなりを利用して模様が刻まれる様は早すぎて目で追うことができませんが、「ブーン」という低い音が響きロクロが数回転する間に仕上がってしまいます。近年新たに加わった「線文(せんもん)」のシリーズは、釉薬を大胆に掻き取り、星座を連想させる文様を描きます。藁灰釉、飴釉、紺釉の3種で構成される品揃えは、それぞれの特徴が効果的に活きるよう土や製法が吟味されており、長年の焼締の製作による、土との対話や焼成技術の蓄積が職人仕事を支えています。

30代後半となった山本さん。修行時代を抜け、最近では思い描いたものを自由に作れる技量が身についた実感があるとのこと。妹と、昨年より姉も加わり兄妹で受け継ぐ国造焼の窯。最近も古作をヒントに新たな製法にチャレンジしていると言います。
※2鳥取民藝協団:戦後、鳥取の民藝運動の復興のため、1949年に組織された。